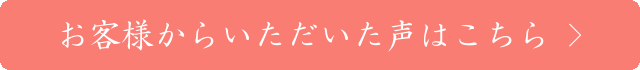行政書士 武原広和事務所 Immigration Procedures Specialist
外国人が日本で就労できる職種・仕事内容
下記の表の【該当する在留資格】欄の在留資格が,いわゆる就労系在留資格です。
この他の在留資格であっても資格外活動許可を受ければ就労が可能となります。
なお,「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」「特別永住者」の在留資格には職業制限はありません。
| 職種例 | 該当する在留資格 |
| 外国政府の外交使節団・領事機関の構成員(外交使節と同様の特権・免除を受ける者を含む) | 外交 |
| 外国政府・国際機関の公務に従事する者 | 公用 |
| 大学、高等専門学校等の教員・研究員 | 教授 |
| 作曲家・画家・彫刻家・著述家等の芸術家 | 芸術 |
| 神官・僧侶・司教・宣教師・伝道師・牧師・神父等 | 宗教 |
| 新聞・雑誌の記者・報道カメラマン等 | 報道 |
| 高度の専門的な能力を有する人材としての大学教授,研究者など | 高度専門職 |
| 会社経営者・管理者,個人事業主 | 経営・管理 |
| 弁護士・司法書士・土地家屋調査士・外国法事務弁護士・公認会計士・外国公認会計士・税理士・社会保険労務士・弁理士・海事代理士・行政書士 | 法律・会計業務 |
| 医師・歯科医師・薬剤師・保健師・助産師・看護師・准看護師・歯科衛生士・診療放射線技士・理学療法士・作業療法士・視能訓練士・臨床工学技士・義肢装具士 | 医療 |
| (政府関係機関・地方公共団体・公社・公団・公益法人・民間企業・外国政府関係機関・国際機関等の)研究者 | 研究 |
| 小・中・高等学校・中等教育学校・特別支援学校・専修学校・各種学校等の教師 | 教育 |
| 機械・電子工学等のエンジニア、システムエンジニア等,設計者,営業職,事務職,通訳者・翻訳者,語学講師,海外取引業務担当者,服飾/室内装飾デザイナー等 | 技術・人文知識・国際業務 |
| 外国にある事業所からの転勤者 | 企業内転勤 |
| 介護福祉士 | 介護 |
| ミュージシャン,ダンサー,俳優,タレント,プロスポーツ選手等 | 興行 |
| 外国料理のコック(料理人),外国様式の建築家,外国人特有製品の修理技能者,毛皮/宝石加工技術者,ペルシャじゅうたん加工師,動物調教師,パイロット,スポーツ指導者,ソムリエ | 技能 |
| 介護,ビルクリーニング,素形材製品/産業機械/電気電子機器等の製造工程の作業・表面処理等の作業,型枠施工/コンクリート圧送/トンネル推進工/建設機械施工/土工/鉄筋施工/とび/海洋土木工/左官/屋根ふき/鉄筋継手/内装仕上げ/表装/建築大工/建築板金/吹付ウレタン断熱/電気通信/配管/保温保冷,船舶の溶接/塗装/鉄工/仕上げ/機械加工/電気機器組立て,自動車整備,航空機地上走行支援業務,航空機の機体・装備品等の整備,旅館・ホテルのフロント/企画・広報/接客,農業,畜産農業,漁業,養殖業,飲食料品(酒類を除く)の製造・加工,飲食物調理/接客/店舗管理など | 特定技能 |
| 技能実習生 | 技能実習 |
| 家事使用人,アマチュアスポーツ選手,外国法事務弁護士,外国の大学の学生のインターンシップ,2025年大阪・関西万博に係る事業に従事する者,EPAによるインドネシア人・フィリピン人・ベトナム人看護師/介護福祉士,外国人建設就労者受入事業によって建設業務に従事する者,外国人造船就労者受入事業によって造船業務に従事する者,製造業外国従業員受入事業によって製造業に従事する者,日系四世,飲食店・小売店での接客業務/ホテル・旅館において翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業等の広報業務・外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフ・ドアマン/タクシー会社において企画・立案や自ら通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー/介護施設において外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら日本語を用いて介護業務に従事する者/食品製造会社において他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行いつつ自らも商品製造ラインに入って作業を行う者,スキーの指導者,起業準備活動者,デジタルノマド,その他 | 特定活動 |
外国人の就労系在留資格の申請
外国人の就労系在留資格の申請は,海外に住んでいる外国人を日本に呼ぶのか,日本に住んでいる外国人を雇用するのか、によって違ってきます。
海外から呼ぶ場合は,在留資格認定証明書交付申請が必要です。在留資格認定証明書は,御本人が日本国大使館や総領事館で就業査証(いわゆる就労ビザ)の発給申請をする際に必要となります。また,日本の入国審査のときにも必要です。
日本に住んでいる外国人を雇用する手続きとしては,在留資格変更許可申請や在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などが必要となる場合があります。
どの申請手続きも,日本国内の地方出入国在留管理局(よく「入管」と呼ばれます)の窓口またはオンラインで申請します。
コンビニや飲食店などで働いている外国人の在留資格
コンビニや飲食店などで働いている外国人の多くは留学か家族滞在の在留資格を持つ外国人ですが,永住者,日本人の配偶者等,永住者の配偶者等,定住者,特定活動,その他の在留資格を持っている場合もあります。
留学は、その名のとおり日本の大学や短大、専門学校などに在籍している留学生です。家族滞在は、例えば、日本に何らかの就労系の在留資格で暮らしている外国人の配偶者か子どもです。
留学や家族滞在の在留資格の外国人は、資格外活動許可を得ると時間制限と職業に制限がありますが、アルバイトをすることができます。
工場などで働いている外国人の在留資格
工場などで働いている外国人の多くは技能実習生です。OTIT外国人技能実習機構ではこのように技能実習制度を紹介しています。
技能実習制度は、我が国で培われた技能、技術又は知識の開発途上地域等への移転を図り、当該開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的として創設された制度です。
その他には特定技能の在留資格で働いている外国人もいますし,留学生や家族滞在などの在留資格を持つ外国人が資格外活動許可を得て働いていることもあります。
就労系在留資格の申請が不許可にならないために
留学から就労系の在留資格への在留資格変更許可申請が不許可となると御本人を雇用することはできません。
在留資格変更許可申請の許可を得るには,最低でも申請する在留資格に該当し,かつ,法定要件を満たしていることが必要です。
さらには雇用する側(企業や個人,法人,団体など)の経営規模や経営状況も審査されます。
したがって,在留資格変更許可申請は本人だけにまかせるのではなく,雇用会社の担当者なども一緒になって検討していくべきでしょう。
海外にいる外国人の就労系在留資の申請
海外にいる外国人を招へいする場合は、在留資格認定証明書交付申請をしますが,当該外国人の就労予定場所(都道府県)を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所でも可能)に申請書や立証資料を提出します。申請は出入国在留管理局の窓口ですることもできますし,オンラインで申請することもできます。
審査の結果、無事に在留資格認定証明書が交付されれば、当該証明書を本人の手元まで届け(電子在留資格認定証明書の場合は本人に送信して)、現地の日本大使館や総領事館で就業ビザを申請する際に添付してもらいます。
審査の結果、無事にビザが発給されれば来日していただけます。
日本国内にいる外国人の就労系在留資格の申請
日本国内で暮らしている外国人を雇用するケースとしては、大学や専門学校を卒業した留学生(留学の在留資格を持つ外国人学生)を雇用するケースが多いと思います。
その場合は本人の在留資格を留学から就労系の在留資格に変更してもらう必要がありますが、本人の住所(都道府県)を管轄する地方出入国在留管理局(支局・出張所でも可能)に申請書や立証資料を提出します。手続きは本人まかせにしないほうが良いです。
また,中途採用をすることもあると思いますが、この場合は、在留カードを見せてもらって現に何の在留資格を持っているかを確認すべきです。
当該外国人が有している在留資格と転職先の仕事内容の関係により、特に何らかの手続きを経ることなく採用することができる場合があります。
しかし、転職先の仕事内容が、外国人の就労許可の対象であることが明確であれば良いですが、そうでない場合は更新手続きの際に不許可になることもありますので、地方出入国在留管理局に就労資格証明書の交付申請をしておいたほうが良いでしょう。
一口に外国人の就労系在留資格といっても上記の表のようにいくつもありますし,それぞれに要件がありますから,一般の方がお分かりにならなくても無理はありません。さらにやっかいなのが申請先の地方出入国在留管理局によっても独自の審査方針がある場合がありますので,そういったことも考慮しなければならない場合もあります。
申請のために用意する立証資料は,外国人を雇用する企業,法人,個人,団体の事業規模によって異なりますが,適切な立証資料を提出すべきです。要件とは関係ない資料をいくら提出しても意味がありませんし,かえって審査担当者を困惑させることになるかも知れません。
申請書の書き方自体は,地方出入国在留管理局(本局など規模の大きいところにはインフォメーションがあります)に聞けば教えてくれますが,それはあくまで形式上のことですから,申請者側の意図を汲んだうえで書き方を教えてくれるわけではありません。したがって,地方出入国在留管理局の職員から書き方を教えてもらったのに不許可となってしまった,というようなことも当然あり得ます。
【行政行政書士 武原広和事務所に御依頼いただけること】
- 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などにかかる書類作成相談を全国どちらからでも御依頼いただけます。面談による御相談を希望なさる場合は,お客様の事業所で行います。
- 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請など申請書その他の書類を作成いたします。
- 在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請,在留期間更新許可申請,就労資格証明書交付申請などの申請代行をいたします。全国どちらの地方出入国在留管理局にも申請することができます。また,オンライン申請にも対応しております。
行政書士 武原広和事務所は、平成14年より外国人の就労系在留資格の申請を取り扱っており、様々な事例を経験しております。これまでの豊富な業務経験から外国人雇用の可能性をアドバイスいたします。
外国人の就労系在留資格の申請で無事に許可を得るためには,どのような立証資料を準備するかが重要なポイントとなりますが,長年の業務経験から審査担当者がどの点に注目して審査しているのかが分かっておりますので,案件ごとにどのような立証資料を御準備いただくとよいか的確にアドバイスを差し上げます。
外国人の就労系在留資格の申請においては当方が申請書の作成を代行いたしますが,場合によって業務内容や雇用に至った経緯などの事情を詳しく説明した理由書なども提出したほうが審査がスムーズとなる場合がありますので,そのような場合も審査担当者に分かりやすいように作成いたします。
全国どちらからでも外国人の就労系在留資格の申請代行をお申し込みいただけます。お客様が貴重な時間を削って地方出入国在留管理局に出頭なさる必要がなくなりますし,審査担当者とのやりとりもおまかせいただけます。